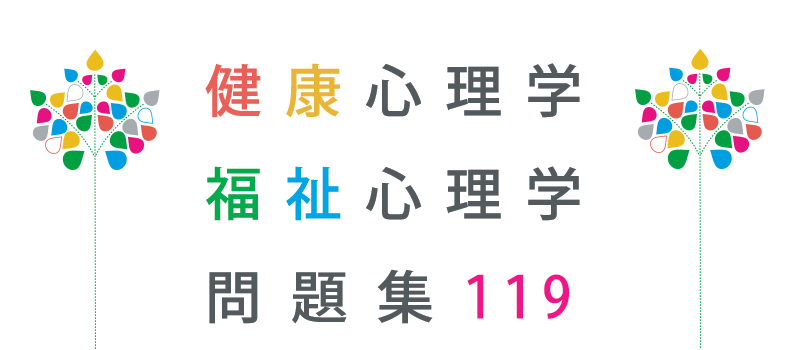音楽療法は、わが国では心理学の専門家よりも、音楽を専門とする側からの関心が高く、世間ではなじみがある技法名、少なくとも外形的にはイメージしやすいアプローチである一方で、臨床心理士指定大学院など、心理臨床家の養成に主眼をおいた課程で専門的に学ぶ機会はまずないなど、独特の位置をとる技法です。日本音楽療法学会や九州臨床音楽療法学会といった専門学会に、臨床心理士や精神保健福祉士は少ないです。
対象者が表現することに重心をおくものは能動的音楽療法、聴取するほうに重心があるのは受容的音楽療法として区分されます。たとえば、発達障害児を含む子どもへの適用が多いノードフ-ロビンズ音楽療法は能動的療法、近年ではマインドフルネスと関連づけた展開もみられる調整的音楽療法は受容的療法となります。ほかにも、音楽療法にはさまざまな流派があり、技術や思想の中心のおき方が根本的に異なるものもたくさんありますので、気をつけてください。わざわざ音楽中心音楽療法(K. エイゲン著、春秋社)と名のるものがあるくらいです。
そのような中でも、古典的な原理として知られるものに、Altshuler, I.M.による同質の原理があります。なお、出題文にある個別性の原則は、バイステックの7原則のひとつです。この7原則については、問74解説も参照してください。
以上より、正解は2となります。こういった組みあわせ問題は、自信のないところがあっても、ほかがわかればしぼれますので、あわてず、あきらめずに解きましょう。この設問は、3か所のうち2か所がわかれば、それがどの2か所であっても、絶対に正解できるようにつくりました。