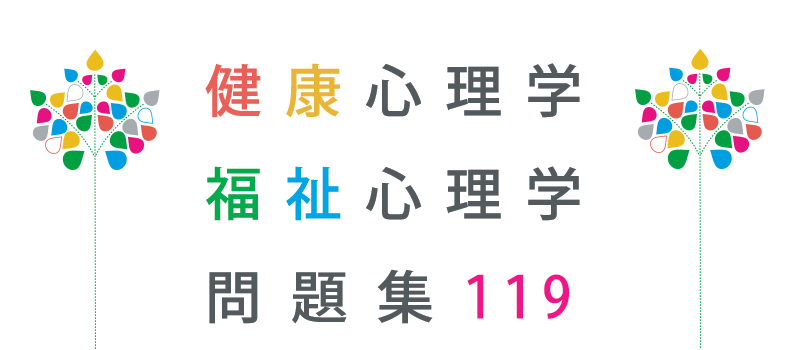健康行動に関するモデルには、いろいろなものがあります。名前から内容がイメージしにくいものも多いですし、そこに提唱者も対応させるのは、意外に覚えにくいところですので、気をつけてください。
1、TTMはProchaska, J.O.らが提唱したものです。Ajzen, I.は、計画的行動理論の提唱を主導しました。
2、健康信念モデルはBecker, M.H.とMainman, L.A.が提唱したものです。Green, L.W.は健康教育のプリシードモデルを提唱し、これがプリシード-プロシードモデルへと発展しました。
3、計画的行動理論はAjzen, I.らが提唱したものです。Prochaska, J.O.は、TTMを提唱しました。
4が正解です。Rogers, R.W.は、健康への脅威の評価と対処行動の評価とが予防行動を動機づけるという、予防動機づけ理論を提唱しました。なお、クライエント中心療法やエンカウンターグループを考案したRogers, C.R.や、イノベーションの普及(翔泳社)を著しイノベーター理論を提唱したRogers, E.M.とは別人です。