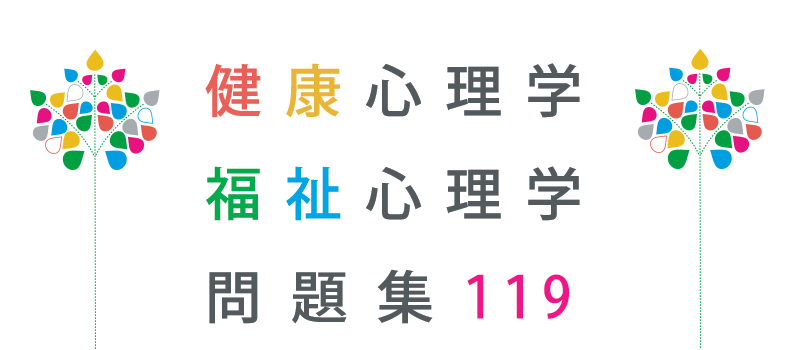新しいタイプのうつ病の問題が広く知られるようになりました。古典的なメランコリー型ではないという文字どおりの意味でも、非定型うつ病と表現が以前からあるほか、現代型、未熟型、逃避型、ディスチミア親和型といったものが提唱され、メディアでも知られる精神科医からは、「社会的うつ病」「30代うつ」「5時までうつ」などの表現も出ています。DSMで見るなら、うつ病とは別のカテゴリで、抑うつをともなう適応障害と考えるほうががなじむという見方もあります。
1、不眠はメランコリー型でよくある身体症状です。「新型」では、むしろ過眠の傾向がみられます。
2、自責感はメランコリー親和型のパーソナリティ特徴とそのまま対応する、自殺にもつながる認知面の症状です。「新型」では、むしろ他責的な傾向がみられます。自分はうつ病で苦しむ被害者で、他人や環境、社会のせいでこうなったと主張します。
3、食欲不振はメランコリー型でよくある身体症状です。「新型」では、食欲はよく出て、不健康そうにやせていくうつ病のイメージとは異なり、太ることも意外にあります。なお、精神科看護白書 2010→2014(精神看護出版)は非定型うつ病の特徴として、「著名な体重増加,または食欲の低下」とDSM-Ⅳにあるように書きましたが、誤りです。DSM-5での表現でみると、「有意の体重増加または食欲増加」です。
4が正解です。明るいできごとで明るい気分に、暗いできごとで暗い気分にと、できごとに反応して気分が変わることを、気分反応性と呼びます。健常者であればあたりまえにあることですが、メランコリー型のうつ病では、気分反応性が大きくそこなわれて、以前に好きだったこと、楽しいはずのことも楽しめなくなります。一方で、「新型」では気分反応性がありますので、うつ病だと公言し、仕事などやりたくないことは受けつけない一方で、休暇や遊びの時間になると存分に楽しめます。そのため、単なる仮病やさぼりだと一蹴されたり、メランコリー型のうつ病の人までさぼりだと誤解されて迷惑したりといった問題を生じます。