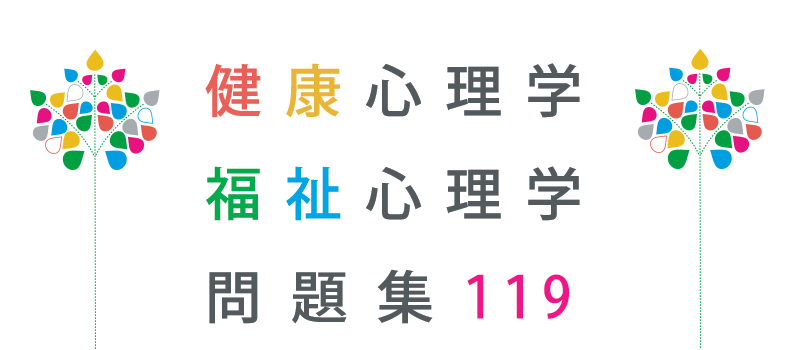エンパワメントは、エンパワーメントとも書かれ、いずれにしてもなじみにくいカタカナ語ですが、ソーシャルワーク領域では重要な概念です。なお、国立国語研究所の第2回「外来語」言い換え提案は、「能力開化」「権限付与」「権限委譲」といった言いかえを提案していますが、あまり定着していません。能力は「開花」と書きたくなりますし、付与や委譲では外部の権力から持たせられる語感があるため、エンパワメントの思想とはずれるようにも思われます。
1、このような始まり方をしたものとして、ノーマライゼーションがあります。英語のnormalizationは、統計の分野では標準化と訳されますが、福祉領域のものはたいてい、カタカナで書きます。そのため誤解されやすいのですが、始まりはデンマークで、わが国ではBank-Mikkelsen, N.E.が、提唱者として有名です。スウェーデンのNirje, B.が広め、Wolfensberger, W.がSRVの概念へと発展させました。なお、第2回「外来語」言い換え提案は、「等生化」「等しく生きる社会の実現」「福祉環境作り」といった言いかえを提案していますが、定着していません。
2が正解です。アメリカ公民権運動を受けて、Solomon, B.B.がBlack Empowerment (Columbia University Press)を著すなどしたことで、福祉領域の概念として広まりました。
(Columbia University Press)を著すなどしたことで、福祉領域の概念として広まりました。
3、このような内容のものとして、AAの12のステップがあります。AAについては、問18解説を参照してください。なお、AA-12とは無関係です。
4、ストレングスと同じ視点ではありませんが、相いれないわけではなく、双方を組みあわせてよりよい効果につなげるのは、すぐれた援助のあり方でしょう。