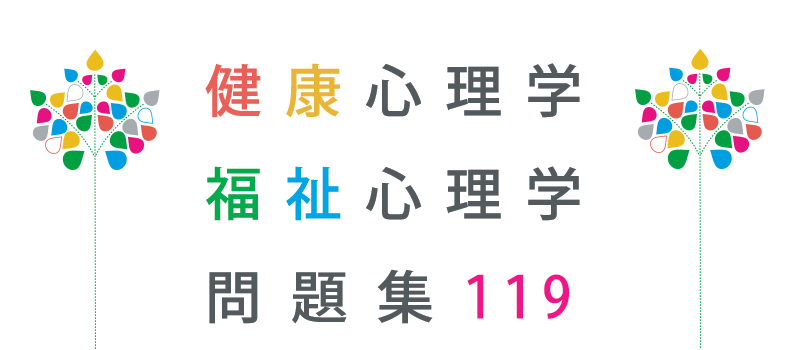H.M.は、1953年に受けたてんかんの根治手術にともなって、特定の記憶機能にのみ、重篤で不可逆的な障害を呈しました。知能は術後も高く、研究に協力的であり続けたため、記憶の認知神経科学を大きく革新し、発展させました。主治医によるぼくは物覚えが悪い 健忘症患者H・Mの生涯(S. コーキン著、早川書房)で、その数奇な生涯を知ることができます。そして、2008年に、82歳で亡くなりました。Lancetに載った訃報記事を示しておきます。
Henry Gustav Molaison, “HM” - The Lancet
1、手術で除去の対象となったのは、海馬を含む両側の側頭葉内側部です。側頭極は、側頭葉で最も吻側に位置し、記憶への関与も指摘されています。
2、短期記憶は術後もほぼ正常でした。また、感覚記憶から、短期記憶を経由せずに、情報が直接に長期記憶へと回ることは、健常者でもみられることです。
3が正解です。手術より前の記憶は、比較的新しいところには想起が困難となる、逆行性健忘が認められましたが、古い記憶には影響がおよんでいませんでした。
4、順向性健忘は顕在記憶に選択的に生じ、新たなエピソード記憶の獲得はほぼ不可能でした。一方で、回転盤追跡課題や不完全線画完成課題などでは、先行経験による明らかな成績向上が現れたことで、想起意識をともなわない記憶である潜在記憶の発見へとつながりました。