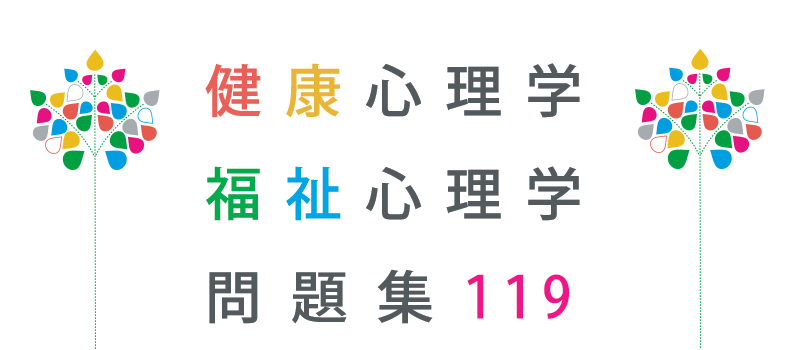BBS会は、更生保護をささえる青年ボランティア団体です。全国に約500ある地区BBS会のほか、大学のサークルとして活動しているものもあります。日本BBS連盟が、最上位の組織として全国の活動を統括しています。
1、BBS運動のはじまりは、1947年の京都少年保護学生連盟の結成だとされます。1950年には、保護司法の成立にともない、保護司の全国団体である全国保護司連盟が結成されました。
2が正解です。兄や姉のようにささえたいという思いから名づけられました。日本BBS連盟の英語名は、Big Brothers and Sisters Movement of Japanとなります。ネット掲示板とも、BOOM BOOM SATELLITESとも無関係です。
3、自立更生促進センターを運営するのは国で、法務省保護局に属します。現在、福島と北九州とにあります。
4、BBS会には自治体等の補助金が入っていますが、資金は潤沢でなくても、破産してはいません。補助金不正でつまずき、2007年に破産したのは、全国精神障害者家族会連合会です。かつてマスコミにも影響力のあった全家連ですが、マスコミに不正を暴かれて、つぶれたのでした。