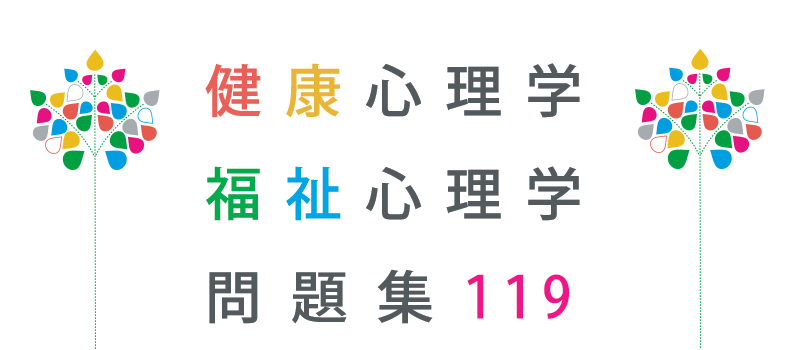DVは、英語のdomestic violenceの略ですので、直訳すれば「家庭内暴力」かもしれませんが、わが国で家庭内暴力というと、思春期以降の子どもから親へふるわれる暴力をイメージしますし、親から子への虐待はDVとは区別されますので、配偶者間暴力と表現されます。
1、DV事例には、劣等感との関連がうかがえるものが、しばしばあります。配偶者がすぐれた特性をもつことに劣等感をあおられて攻撃に走る、被害者側が劣等感や罪悪感にとらわれて援助を求めず継続するなどのパターンがあります。
2、DV防止法は、正式名称を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律といい、いわゆる「でっちあげDV」を横行させるほどに強力なのですが、デートDVへの発動は困難です。改正時に加わった1条3項によって、内縁関係も対象に加えたところまでが、保護命令の射程です。
3、周期性のDV加害のパターンでは、良好な関係であるハネムーン期から、少しずつ険悪な状態が生じてくる準備期ないしは緊張期、大きな暴力行動にいたる爆発期へという展開がみられます。爆発期の後は、加害者は深く反省する態度を示し、それを被害者が許容することでハネムーン期へと戻ります。
4が正解です。このため、DV被害者が、周囲の説得にもかかわらず逃げない、いったん保護されても自分から戻っていくなどして、関係者に徒労感を生みます。ハネムーン期が得られることでの部分強化、たびたび耐えてきたことでのコンコルド効果や認知的不協和、各種の防衛機制などの関与が考えられるでしょう。