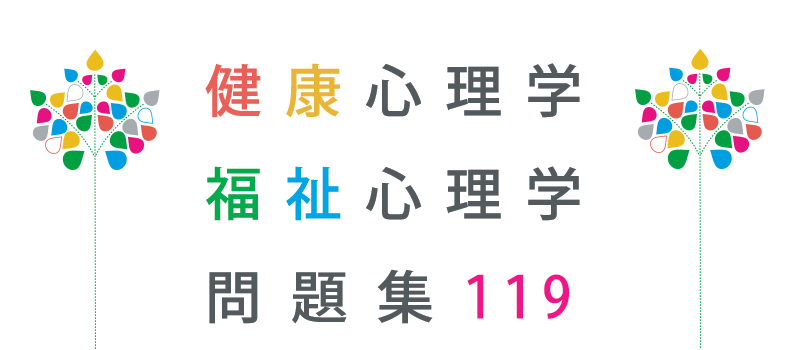一般に、初婚よりも再婚のほうが、その後に離婚にいたる率は高いとされます。ただし、アメリカなどでは出ていますが、わが国の政府統計では、婚姻の時点と異なり、離婚に関して両者を分けた統計はありません。それでも、裁判所による司法統計の家事事件編で、年齢や婚姻期間、別居期間などとの対応を見ることはできます。申し立ての動機に関しては、平成25年度では第19表にまとめられています。
正解は1となります。全体的な件数のかたより、特に「暴力を振るう」での極端なかたよりと、「同居に応じない」でのその反転に注目すると、どちらが夫でどちらが妻か、見わけがつきやすいでしょう。また、初婚-再婚だとすると、これらのパターンにはうまくなじまないことも想像できると思います。